CONTENTS
- « 前の記事
「GOD EATER ONLINE」が帰ってくる!
ストーリーノベル 第十章
「GOD EATER ONLINE」 STORY NOVEL ~10章-エピローグ~
フェンリルからの独立――
その計画を聞いて、俺はようやく合点がいった。
何故、クロエは崖っぷちのヒマラヤ支部を訪れ、助けたのか。
何故、クロエはレイラや俺たちを鍛え、住民たちの信頼を勝ち取ることに熱心だったのか。
何故、クロエはリマリアという危険な力を容認し、その力をより高められるよう仕向けたのか。
全てはフェンリルの手を離れた地――彼女が言うところの、楽園を手にするため。
そのために俺たちは、ずっと彼女の手の平の上で踊らされていたことになる。
(やはり、あの時躊躇わず、神機を振り抜くべきだったか……?)
きっと、俺がクロエ・グレースの命を奪える機会など、もう二度と巡ってこないだろう。
その結果、ヒマラヤ支部はどうなっていくのか……
まだ誰も、その先の未来を見通せずにいた。
「独立、なんて本当に言ったのか?」
「ああ、明言した」
コーヒーカップにゆっくりと口をつけながら、俺はJJの問いかけに答える。
「調査はしたが、彼女の背後にロシア支部はいないぞ」
「だろうな……何かいるとしたら、もっと独自性の強い組織だ」
俺は答えながら、頭の中でぼんやりと考える。
(師匠は、おそらくそこに匿われている……)
最終的には、クロエを泳がせておいた価値はあったと言える。
同じ状況にならなければ、きっとクロエは口を割らなかっただろう。
(それにしても、独立か)
彼女の目的が何だろうが、俺の知ったことではないが……あれもよくよく、面倒ごとが好きな女だ。俺とは生涯相容れることはないだろう。
「おら」
そこで乱暴に、JJがカップにグラスをぶつけてきた。
カップが欠けそうな勢いに、俺は思わず顔をしかめてみせるが、JJに気にした様子はない。
「とりあえず、生きて帰れたことに乾杯だ。おかげで趣味が楽しめる」
「……ごもっともだ」
笑いながら酒をあおるJJを見て、俺もカップを傾ける。
アラガミから作った似非コーヒーの味は、相も変わらず最悪だ。
だが、この苦さは悪くない。戦いの中で覚悟していたものよりずっと――
「どうした。ずいぶんご機嫌じゃねぇか」
「なに……彼にも後で、この味を振る舞ってやろうと思ってな」
「お前なぁ……せっかく我慢して飲んでくれてんだから、あんまりイジメてやるなよな」
「ふっ……」
JJの言葉を無視してコーヒーを呷る。
(悪くないな、実に……)
『この一杯のために生きている』などと嘯く人の気持ちが、今は少しだけ分かる気がする。
広場を訪れると、椅子に腰かけるレイラの姿が目に入った。
一瞬視線が交差すると、つい憎まれ口を叩きたくなったが――ぐっとこらえ、僕は彼女の隣に座った。
「……レイラはクロエ支部長についていくのか?」
「さあ……フェンリル本部の出方次第でしょうね。このまま変わらなければ、フェンリルに属する意義が問われます」
レイラはため息交じりに応える。しかし、クロエの言葉を強く否定したようにも思えなかった。
「意義、か……」
「ヒマラヤ支部に住む人々を誰が守るのか? それがフェンリルでないというのなら……」
「支部というインフラはフェンリルのものだとしても?」
「捨てたものに権利を主張するのは不誠実です。捨てないなら為政者としてすべきことがある、そういうことでしょう」
なるほど……実にクロエ・グレース寄りの意見だ。
以前の僕ならばはっきりとそう口にし、喧嘩になっていた場面だろう。
だが、レイラはクロエの考えを呑み込み、真摯に考え、自分の考えにしようとしている。
今がその過程だとすれば、茶化す気にもなれない。
「……リュウはどうなのです?」
そうして僕が黙っていると、レイラから俺に話を振ってくる。
「独立に向けて動くとしたら、実家に帰りますか?」
「帰るなら引退だな。まだその予定はないが」
肩をすくめながら言う。
「支部の壁を守るのが今は最優先だ。所属がフェンリルであるかどうかは二の次だね」
「二の次、ですか」
「ああ。人ありきでなければ話にならない」
フェンリルにつくか支部長につくかは先の問題だ。まずは目先のことに目を向けておく。
以前なら、消極的だとレイラに怒られていた場面かもしれないが――
「ええ、話になりません」
そうして互いに視線を交わし、すぐに堪えきれなくなって笑い出してしまう。
(変われば変わるもんだな。僕もレイラも……)
こうしてレイラと並び立って、喧嘩もせずに話し合う日が来るなんて、まったく考えもしなかった。
いつ、どうしてこんな風に変わっていったのだろう。
八神さんが来て、ネブカドネザルに負けて、住民たちと騒ぎになって、あの子に出会って――そういう小さな積み重ねが、少しずつ僕を変えていったと思う。
だから僕もレイラも、これからもどんどん変わっていくのだろう。
きっと、独立の話もそのきっかけの一つになる。
そう考えると……場違いなのかもしれないが、僕は少しわくわくしていた。
「何を一人でにやにやしているのですか? 人が真面目な話をしている最中に」
「……なんだと?」
訂正する。
僕とレイラの関係は、これからも変わりそうにない。
「やっぱり仲良しだな、あの二人は」
レイラとリュウのやり取りを受付から眺めていると、ドロシーがおかしそうに言う。
「ふふ。二人とも根が真面目なのよ」
「ほー。隙あらば休日もオペレートしようとするド真面目さんが言うかね?」
「いいでしょー!」
冗談っぽく言うドロシーに向け、私は頬を膨らませて答えた。
「よかないって。倒れる度に抱っこして部屋に放り込む身にもなってくれよな」
「軽々放り込まれる身にもなっていいのよ!」
私の言葉に、ドロシーはとびっきりの笑顔を見せる。
「んで、もしフェンリルから独立したらどうなるんだい? 店賃安くなる?」
「知らないわよ! あ、でも、物資の確保が心配じゃない……?」
「うおっ。それはたしかに……でもまあ、中国支部、ロシア支部との関係性は変わんないか」
「あ……」
「ん? どうしたカリーナ?」
「いや、多分だけど、クロエ支部長がフェンリル支部と関わりの薄い支部を取引相手に選んだのって……」
私の言葉の意味を飲み込んだドロシーが、大げさに両腕を抱えてみせる。
「……やっぱあの人、おっそろしーな」
「うん……」
結局、クロエ支部長は計画を私たちに打ち明けてくれたわけだけど、それがいいことなのかどうか、私にはまだ判断がつかずにいる。
それにあの人のことだから、まだ隠しごとの一つや二つ持ってそうだし、ゴドーさんはゴドーさんで、また厄介ごとを押し付けてきそうだし……
なんというか、前途多難……先のことを考えると、どうしても不安が先に来る。
(できれば大きな争いもなく、皆が無事でいられるといいけど……)
そんな風に考えていると、ドロシーが冗談っぽく笑いかけてくる。
「ま、大丈夫だって。あたしらはしたたかにやってくだけだ!」
「……たしかに。アラガミと戦うのは変わらないものねえ」
普段と変わらない調子の彼女が可笑しくて、私も自然と笑みを返せた。
支部長室の窓から見える、外の景色に目をやる。
すでに夜の帳は降りていて、広大なヒマラヤの大地にはただ薄闇がどこまでも広がっている。
私の門出を祝福する景色とは、とても言い難い。
「……賽は、投げた」
確かめるようにして、小さく呟く。
投げられたのではない。私がこの手で投げたのだ。
それは疑いようのない事実。だが――
「……出目を決めるのは私ではない」
そのことが虚しくもあり、少し愉快なことだとも思う。
この世の全てが誰かに決められているのだとすれば、なんと面白みのないことだろう。
人の力の及ぶことは限られている。おかげでフェンリルは不変の支配者足り得ないと言い切れるし、私も足掻きようがあるのだ。
「…………」
手元に視線を落とし、そこにある絵葉書を見つめる。
そこに描かれているのは、かつてあったモスクワの街並みだ。
もう、ずいぶんと年季が入ってしまった。
それだけ月日が経ってしまったらしい。
しかし私にとっては、今も――
「…………楽園、か」
呟きは、虚空のなかへと吸い込まれていく。
「あの、いろいろ……ありました」
「……ああ」
マリアの墓の前に立ってから、どれくらい時間が経った頃だろう。
俺がわずかに姿勢を崩したのを見て、リマリアが声をかけてきた。
本当に、いろんなことがあった。
今回の戦いについても、リマリアと出会ってからもそうだ。
はじめてネブカドネザルやクベーラと対面した時のことが、今は遥か昔のことのようだ。
仲間たちやリマリアのことも、ずっと昔から知っていたような気がする。
そんな中でも、彼女が隣にいた頃のことだけが、昨日のことのように感じられる。
(いや、もしかしたら本当に――)
俺はリマリアの手元で輝くリングにちらりと目を向けた。
あの戦いの中、アラガミになりかけた俺を、マリアは救いに来てくれたという。
だが、それよりずっと前から……そして今も。
マリアはずっと、俺の隣にいてくれているんじゃないだろうか。
そんな風に考えていると、リマリアが小さく俯いたのが見えた。
「……大丈夫か?」
少しだけ緊張しながら、自分からリマリアに声をかける。
リマリアは一瞬取り繕おうとしたようだったが、俺の目を見ると、ゆっくり頷いた。
「――今の気持ちを告白すると、不安……です」
リマリアは胸に手を当てながら、ゆっくりと言葉を紡いでいく。
「私一人では、また……神機の力が暴れるのを止められないと、思っていて……」
「…………」
「マリアは大丈夫だと言ってくれたのですが、私はあなたに頼らなくてはいけません。それが、申し訳なくて……不安で……苦しい、です」
「……そうか」
感情に押しつぶされそうになりながらも、リマリアは自分の想いを言葉にしていく。
俺はそれを静かに聞きながら、空を見上げた。
「邪魔に、なったら……いつでも言ってください。その時は……」
「邪魔になんてならない」
「え……?」
言葉を遮り、俺は彼女をじっと見つめた。
「忘れたか? あの時約束した言葉……」
「あ……」
リマリアはすぐに思い当たった様子だ。
あの日、俺が彼女に伝えた約束を――
正直、こうして面と向かって伝えていくのはどうも照れ臭いものがある。
しかし、つい先日ゴドーからも注意を受けたばかりだ。
人間関係の基本は会話――受け身に徹するのはやめだ。
「……お前とずっと一緒にいる。俺はあの日、お前にそう伝えたな」
「……っ。はい」
「だけど、あれは一旦なしにしよう」
「えっ……!?」
俺の言葉に、リマリアが傷ついたような表情をする。
……しまったな。どうやら俺は、伝え方を間違えているらしい。
「違うんだ、その……。あの約束は、俺が一方的に取り付けたものだったから、あの言い方は、なしにしたい」
しどろもどろになりながら、何とか言葉を紡いでいく。
リマリアは、そんな俺の姿をじっと見つめて、待ってくれているのだが――そうされることで、尚更言葉が見つからなくなる。
まいったな……こういうやり取りは、これまで戦ったどんな相手よりもやりにくい。
だけど――それでも俺は、不器用に言葉を並べておこうと思った。
リマリアに、俺の想いを伝えたいと思ったから……
「……不安なのは、俺も同じだ。支部がこの先どうなっていくのか……俺の力が、どこまで通用するのか。リマリアや仲間たちを、本当に守っていけるのか……」
「セイ、さん……」
「俺はこれまで、大切なものをたくさん失ってきたから。大事なものを守り切る力は、俺にはなくて。……不器用で、不完全な、出来損ないが、俺だから」
「……っ。そんなことありません! セイさんは、すごく強くて素敵な人ですっ!」
リマリアが頭を振って言う。俺はそれを見て……ちょっと迷ってから、静かに聞き返す。
「……そうかな?」
「そうです!」
「じゃあ……そうかな」
「…………」
さすがに照れくさくて、俺は彼女から顔を背けることしかできず。彼女がどんな顔をしたのかは分からなかった。
――失敗作、出来損ない。
俺はずっと、自分のことをそういうものとして捉えていたし、周りからどう言われようと、それが変わることはないと思っていた。
だけど……彼女と二人でなら。俺も少しずつ、変わっていけるのかもしれない。
そう思えたから、俺はリマリアの隣にいたい。
彼女や仲間たちのために必要だからではなくて……ただ、俺がそうしたいから。
「リマリア」
「はい」
「……ずっと、一緒にいてくれるか?」
かくして俺は、どうしようもなく言いづらかったその一言を、彼女に告げた。
鼓動が早くなり、手に汗が滲む。
恐怖と高揚感で思考が鈍るのを感じながら、恐る恐る彼女を見る。
すると彼女は、笑っていた。
いつかこの場所で見せてくれた、どこかぎこちないそれではなく。
ごく自然に、優しく、温かく。
眩しいものを見るようにそっと目を細めた彼女が、紅が差した頬に満面の笑みを浮かべている。
俺の思考を吹き飛ばすように、一陣の風が吹き抜ける。
「はいっ!」
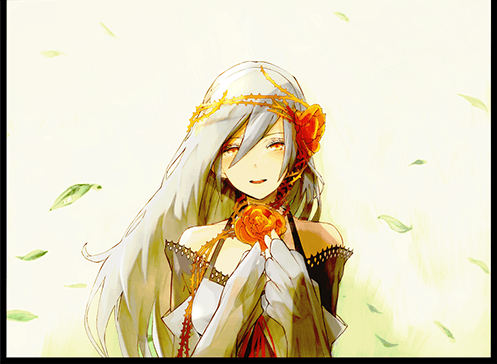
答えて笑う彼女の手元で、玩具のリングがきらりと光った。
フェンリルからの独立――
その計画を聞いて、俺はようやく合点がいった。
何故、クロエは崖っぷちのヒマラヤ支部を訪れ、助けたのか。
何故、クロエはレイラや俺たちを鍛え、住民たちの信頼を勝ち取ることに熱心だったのか。
何故、クロエはリマリアという危険な力を容認し、その力をより高められるよう仕向けたのか。
全てはフェンリルの手を離れた地――彼女が言うところの、楽園を手にするため。
そのために俺たちは、ずっと彼女の手の平の上で踊らされていたことになる。
(やはり、あの時躊躇わず、神機を振り抜くべきだったか……?)
きっと、俺がクロエ・グレースの命を奪える機会など、もう二度と巡ってこないだろう。
その結果、ヒマラヤ支部はどうなっていくのか……
まだ誰も、その先の未来を見通せずにいた。
「独立、なんて本当に言ったのか?」
「ああ、明言した」
コーヒーカップにゆっくりと口をつけながら、俺はJJの問いかけに答える。
「調査はしたが、彼女の背後にロシア支部はいないぞ」
「だろうな……何かいるとしたら、もっと独自性の強い組織だ」
俺は答えながら、頭の中でぼんやりと考える。
(師匠は、おそらくそこに匿われている……)
最終的には、クロエを泳がせておいた価値はあったと言える。
同じ状況にならなければ、きっとクロエは口を割らなかっただろう。
(それにしても、独立か)
彼女の目的が何だろうが、俺の知ったことではないが……あれもよくよく、面倒ごとが好きな女だ。俺とは生涯相容れることはないだろう。
「おら」
そこで乱暴に、JJがカップにグラスをぶつけてきた。
カップが欠けそうな勢いに、俺は思わず顔をしかめてみせるが、JJに気にした様子はない。
「とりあえず、生きて帰れたことに乾杯だ。おかげで趣味が楽しめる」
「……ごもっともだ」
笑いながら酒をあおるJJを見て、俺もカップを傾ける。
アラガミから作った似非コーヒーの味は、相も変わらず最悪だ。
だが、この苦さは悪くない。戦いの中で覚悟していたものよりずっと――
「どうした。ずいぶんご機嫌じゃねぇか」
「なに……彼にも後で、この味を振る舞ってやろうと思ってな」
「お前なぁ……せっかく我慢して飲んでくれてんだから、あんまりイジメてやるなよな」
「ふっ……」
JJの言葉を無視してコーヒーを呷る。
(悪くないな、実に……)
『この一杯のために生きている』などと嘯く人の気持ちが、今は少しだけ分かる気がする。
広場を訪れると、椅子に腰かけるレイラの姿が目に入った。
一瞬視線が交差すると、つい憎まれ口を叩きたくなったが――ぐっとこらえ、僕は彼女の隣に座った。
「……レイラはクロエ支部長についていくのか?」
「さあ……フェンリル本部の出方次第でしょうね。このまま変わらなければ、フェンリルに属する意義が問われます」
レイラはため息交じりに応える。しかし、クロエの言葉を強く否定したようにも思えなかった。
「意義、か……」
「ヒマラヤ支部に住む人々を誰が守るのか? それがフェンリルでないというのなら……」
「支部というインフラはフェンリルのものだとしても?」
「捨てたものに権利を主張するのは不誠実です。捨てないなら為政者としてすべきことがある、そういうことでしょう」
なるほど……実にクロエ・グレース寄りの意見だ。
以前の僕ならばはっきりとそう口にし、喧嘩になっていた場面だろう。
だが、レイラはクロエの考えを呑み込み、真摯に考え、自分の考えにしようとしている。
今がその過程だとすれば、茶化す気にもなれない。
「……リュウはどうなのです?」
そうして僕が黙っていると、レイラから俺に話を振ってくる。
「独立に向けて動くとしたら、実家に帰りますか?」
「帰るなら引退だな。まだその予定はないが」
肩をすくめながら言う。
「支部の壁を守るのが今は最優先だ。所属がフェンリルであるかどうかは二の次だね」
「二の次、ですか」
「ああ。人ありきでなければ話にならない」
フェンリルにつくか支部長につくかは先の問題だ。まずは目先のことに目を向けておく。
以前なら、消極的だとレイラに怒られていた場面かもしれないが――
「ええ、話になりません」
そうして互いに視線を交わし、すぐに堪えきれなくなって笑い出してしまう。
(変われば変わるもんだな。僕もレイラも……)
こうしてレイラと並び立って、喧嘩もせずに話し合う日が来るなんて、まったく考えもしなかった。
いつ、どうしてこんな風に変わっていったのだろう。
八神さんが来て、ネブカドネザルに負けて、住民たちと騒ぎになって、あの子に出会って――そういう小さな積み重ねが、少しずつ僕を変えていったと思う。
だから僕もレイラも、これからもどんどん変わっていくのだろう。
きっと、独立の話もそのきっかけの一つになる。
そう考えると……場違いなのかもしれないが、僕は少しわくわくしていた。
「何を一人でにやにやしているのですか? 人が真面目な話をしている最中に」
「……なんだと?」
訂正する。
僕とレイラの関係は、これからも変わりそうにない。
「やっぱり仲良しだな、あの二人は」
レイラとリュウのやり取りを受付から眺めていると、ドロシーがおかしそうに言う。
「ふふ。二人とも根が真面目なのよ」
「ほー。隙あらば休日もオペレートしようとするド真面目さんが言うかね?」
「いいでしょー!」
冗談っぽく言うドロシーに向け、私は頬を膨らませて答えた。
「よかないって。倒れる度に抱っこして部屋に放り込む身にもなってくれよな」
「軽々放り込まれる身にもなっていいのよ!」
私の言葉に、ドロシーはとびっきりの笑顔を見せる。
「んで、もしフェンリルから独立したらどうなるんだい? 店賃安くなる?」
「知らないわよ! あ、でも、物資の確保が心配じゃない……?」
「うおっ。それはたしかに……でもまあ、中国支部、ロシア支部との関係性は変わんないか」
「あ……」
「ん? どうしたカリーナ?」
「いや、多分だけど、クロエ支部長がフェンリル支部と関わりの薄い支部を取引相手に選んだのって……」
私の言葉の意味を飲み込んだドロシーが、大げさに両腕を抱えてみせる。
「……やっぱあの人、おっそろしーな」
「うん……」
結局、クロエ支部長は計画を私たちに打ち明けてくれたわけだけど、それがいいことなのかどうか、私にはまだ判断がつかずにいる。
それにあの人のことだから、まだ隠しごとの一つや二つ持ってそうだし、ゴドーさんはゴドーさんで、また厄介ごとを押し付けてきそうだし……
なんというか、前途多難……先のことを考えると、どうしても不安が先に来る。
(できれば大きな争いもなく、皆が無事でいられるといいけど……)
そんな風に考えていると、ドロシーが冗談っぽく笑いかけてくる。
「ま、大丈夫だって。あたしらはしたたかにやってくだけだ!」
「……たしかに。アラガミと戦うのは変わらないものねえ」
普段と変わらない調子の彼女が可笑しくて、私も自然と笑みを返せた。
支部長室の窓から見える、外の景色に目をやる。
すでに夜の帳は降りていて、広大なヒマラヤの大地にはただ薄闇がどこまでも広がっている。
私の門出を祝福する景色とは、とても言い難い。
「……賽は、投げた」
確かめるようにして、小さく呟く。
投げられたのではない。私がこの手で投げたのだ。
それは疑いようのない事実。だが――
「……出目を決めるのは私ではない」
そのことが虚しくもあり、少し愉快なことだとも思う。
この世の全てが誰かに決められているのだとすれば、なんと面白みのないことだろう。
人の力の及ぶことは限られている。おかげでフェンリルは不変の支配者足り得ないと言い切れるし、私も足掻きようがあるのだ。
「…………」
手元に視線を落とし、そこにある絵葉書を見つめる。
そこに描かれているのは、かつてあったモスクワの街並みだ。
もう、ずいぶんと年季が入ってしまった。
それだけ月日が経ってしまったらしい。
しかし私にとっては、今も――
「…………楽園、か」
呟きは、虚空のなかへと吸い込まれていく。
「あの、いろいろ……ありました」
「……ああ」
マリアの墓の前に立ってから、どれくらい時間が経った頃だろう。
俺がわずかに姿勢を崩したのを見て、リマリアが声をかけてきた。
本当に、いろんなことがあった。
今回の戦いについても、リマリアと出会ってからもそうだ。
はじめてネブカドネザルやクベーラと対面した時のことが、今は遥か昔のことのようだ。
仲間たちやリマリアのことも、ずっと昔から知っていたような気がする。
そんな中でも、彼女が隣にいた頃のことだけが、昨日のことのように感じられる。
(いや、もしかしたら本当に――)
俺はリマリアの手元で輝くリングにちらりと目を向けた。
あの戦いの中、アラガミになりかけた俺を、マリアは救いに来てくれたという。
だが、それよりずっと前から……そして今も。
マリアはずっと、俺の隣にいてくれているんじゃないだろうか。
そんな風に考えていると、リマリアが小さく俯いたのが見えた。
「……大丈夫か?」
少しだけ緊張しながら、自分からリマリアに声をかける。
リマリアは一瞬取り繕おうとしたようだったが、俺の目を見ると、ゆっくり頷いた。
「――今の気持ちを告白すると、不安……です」
リマリアは胸に手を当てながら、ゆっくりと言葉を紡いでいく。
「私一人では、また……神機の力が暴れるのを止められないと、思っていて……」
「…………」
「マリアは大丈夫だと言ってくれたのですが、私はあなたに頼らなくてはいけません。それが、申し訳なくて……不安で……苦しい、です」
「……そうか」
感情に押しつぶされそうになりながらも、リマリアは自分の想いを言葉にしていく。
俺はそれを静かに聞きながら、空を見上げた。
「邪魔に、なったら……いつでも言ってください。その時は……」
「邪魔になんてならない」
「え……?」
言葉を遮り、俺は彼女をじっと見つめた。
「忘れたか? あの時約束した言葉……」
「あ……」
リマリアはすぐに思い当たった様子だ。
あの日、俺が彼女に伝えた約束を――
正直、こうして面と向かって伝えていくのはどうも照れ臭いものがある。
しかし、つい先日ゴドーからも注意を受けたばかりだ。
人間関係の基本は会話――受け身に徹するのはやめだ。
「……お前とずっと一緒にいる。俺はあの日、お前にそう伝えたな」
「……っ。はい」
「だけど、あれは一旦なしにしよう」
「えっ……!?」
俺の言葉に、リマリアが傷ついたような表情をする。
……しまったな。どうやら俺は、伝え方を間違えているらしい。
「違うんだ、その……。あの約束は、俺が一方的に取り付けたものだったから、あの言い方は、なしにしたい」
しどろもどろになりながら、何とか言葉を紡いでいく。
リマリアは、そんな俺の姿をじっと見つめて、待ってくれているのだが――そうされることで、尚更言葉が見つからなくなる。
まいったな……こういうやり取りは、これまで戦ったどんな相手よりもやりにくい。
だけど――それでも俺は、不器用に言葉を並べておこうと思った。
リマリアに、俺の想いを伝えたいと思ったから……
「……不安なのは、俺も同じだ。支部がこの先どうなっていくのか……俺の力が、どこまで通用するのか。リマリアや仲間たちを、本当に守っていけるのか……」
「セイ、さん……」
「俺はこれまで、大切なものをたくさん失ってきたから。大事なものを守り切る力は、俺にはなくて。……不器用で、不完全な、出来損ないが、俺だから」
「……っ。そんなことありません! セイさんは、すごく強くて素敵な人ですっ!」
リマリアが頭を振って言う。俺はそれを見て……ちょっと迷ってから、静かに聞き返す。
「……そうかな?」
「そうです!」
「じゃあ……そうかな」
「…………」
さすがに照れくさくて、俺は彼女から顔を背けることしかできず。彼女がどんな顔をしたのかは分からなかった。
――失敗作、出来損ない。
俺はずっと、自分のことをそういうものとして捉えていたし、周りからどう言われようと、それが変わることはないと思っていた。
だけど……彼女と二人でなら。俺も少しずつ、変わっていけるのかもしれない。
そう思えたから、俺はリマリアの隣にいたい。
彼女や仲間たちのために必要だからではなくて……ただ、俺がそうしたいから。
「リマリア」
「はい」
「……ずっと、一緒にいてくれるか?」
かくして俺は、どうしようもなく言いづらかったその一言を、彼女に告げた。
鼓動が早くなり、手に汗が滲む。
恐怖と高揚感で思考が鈍るのを感じながら、恐る恐る彼女を見る。
すると彼女は、笑っていた。
いつかこの場所で見せてくれた、どこかぎこちないそれではなく。
ごく自然に、優しく、温かく。
眩しいものを見るようにそっと目を細めた彼女が、紅が差した頬に満面の笑みを浮かべている。
俺の思考を吹き飛ばすように、一陣の風が吹き抜ける。
「はいっ!」
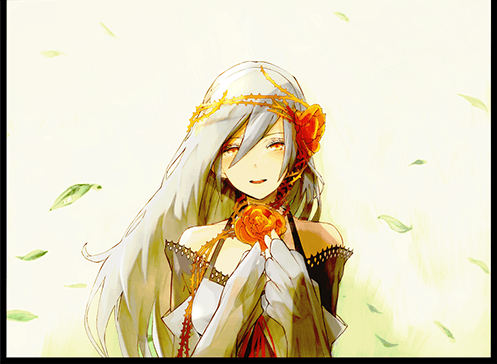
答えて笑う彼女の手元で、玩具のリングがきらりと光った。



