CONTENTS
「GOD EATER ONLINE」が帰ってくる!
ストーリーノベル 第五章
「GOD EATER ONLINE」 STORY NOVEL ~5章-1話~
「よーし、呼んでくれていいぞ、セイ!」
ドロシーが弾んだ声で、俺にゴーサインを出す。
「どの辺ですか? この辺? この辺に出ます?」
「はぁ……どこに出ても同じでしょう。わたくしたちには見えないのですから」
楽しげなカリーナたちの様子に対して、レイラは冷静な姿勢を崩さない。
俺はそんな彼女たちの声を聞きつつ、神機に触れて目を閉じた。
心の中で彼女に呼びかけると、白い髪をなびかせた女性がふわりと目の前に現れる。
姿を現した彼女は、無機質な瞳をこちらに向けた。
「お呼びでしょうか」
「ああ……。彼女たちたっての希望でな」
「彼女たち……?」
首を傾げた純白の女性に対し、俺は視線でレイラたちを見るよう促した。
興味深そうにこちらを見ていたカリーナが口を開く。
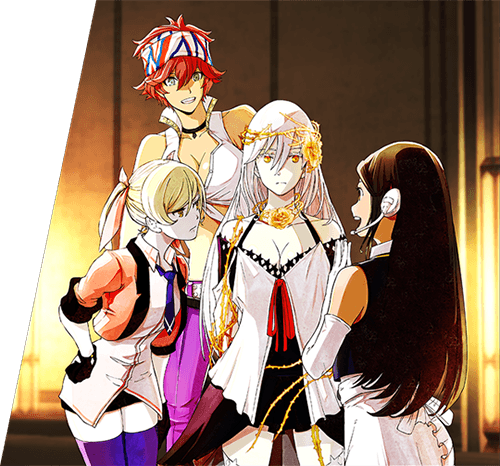 「八神さん、今声の主さんがいるんですね?」
「八神さん、今声の主さんがいるんですね?」
「はい。俺のすぐ隣に立っています」
「ほ、本当ですか? わー、全然分からないです」
じっと目を凝らすカリーナの隣で、レイラは澄ました顔で腕を組んでいる。
「見えず聞こえず、触れず、です。その方は、隊長補佐を介してしか、言葉のやり取りができませんよ」
すでに似たような場面を何度も経験しているためか、レイラは他二人に比べれば落ち着いている。
しかし興味がない訳ではないようで、カリーナたちが囲んだその場所へ流し目を向けている。
「幽霊ってのが本当にいたら、こんな感じなんだろうな。なぁ、声の主さんは憑りついたり、呪ったりはしないのか?」
「そのような機能はありません」
ドロシーの質問に対し、白髪の女性が即座に答える。
「それってつまり……機能があれば呪ったってこと?」
「必要があれば」
「……そこまでにしなさい。その手の話は不愉快よ」
彼女の言葉をそのまま伝えていると、レイラにきつく睨まれた。
質問も返答も、俺のものではないのだが……
「そっかそっか、レイラはこういう話が苦手なんだっけ?」
「なっ……苦手ではありません。くだらないと言っているだけです」
「まあまあ……オカルトじみた話はともかく、特にイヤな気配とかもないですし、安全、ということでいいんですよね?」
「……はい。問題ないと思います」
少なくとも、彼女が俺に危害を加えたことは一度もない。
しかし、どうしてそんなことを尋ねるのだろう。
「結局、ご用件はなんなのでしょうか」
「……分からない」
それは俺も聞きたいところだった。
ドロシーに捕まり、神機を持って来いと言われ、なし崩し的に彼女を呼び出すことになった。
盛り上がる女性陣を前に、なんとなく居心地の悪さを感じていると、不意にドロシーがこちらを向いて宣言した。
「よーし! じゃ、マリア声の主さんを交えた、トークパーティの始まりだぜ!」
「わー! よろしくお願いしまーす!」
「トークパーティ……ですか?」
俺との声がぴたりと重なる。
トークパーティ……つまりは一般に女子会、ガールズトークと呼称されるものの類だろうか。
つまり俺は、ドロシーが言うところの『マリア声の主さん』の召喚と通訳のためにここに呼び出されたらしい。
……十中八九、必要がなければ一生縁のなかった場面だろう。
(一体、どんな話をすればいいんだ? ……いや、主賓じゃないから黙っていればいいのか)
とはいえ隣に立つ無表情な彼女が、楽しくトークパーティする姿も想像がつかない。
パチパチと拍手をするカリーナの隣で、レイラが深い溜息をつく。
「成立するのかしら、これ……」
「成立するんじゃない。成立させるんだよ、隊長補佐がな!」
ドロシーの腕がぐっと伸び、強引に俺の肩に回された。
俺が成立させるのか? 司会進行やトークスキルの低さは、周知の事実だと思うのだが……
そうして悩んでいると、それを察してか彼女が声をかけてくる。
「私は何をすればいいのでしょうか?」
「……そうだな、彼女たちの質問に答えてあげてくれ」
「分かりました」
苦し紛れにそう言うと、女性はすんなり頷いてくれた。
丸投げするようで申し訳ないが、俺一人ではこの場を乗り切ることは不可能だ。
……それにしても彼女は、その姿こそマリアに近いが、どこまでも俺の言葉に従順だ。
(マリアなら、すんなり協力はしてくれなかっただろうな……)
きっと成長を促すために、率先して俺が場を仕切るように仕向けただろう。
この女性はマリアとは違い、俺の言うことに逆らわない。
だからこそ浮き彫りになる。やはり彼女は、俺の家族とは別人なのだと。
「じゃあ、質問がある人から順番にどうぞ」
俺がそう言うと、真っ先にドロシーが手を挙げた。
「はいはい! まず、これは訊きたかったんだけどさ、声の主さんとマリアって、どっちが美人さんなの?」
「えっ、いきなりそこ!?」
真剣な表情で尋ねるドロシーに向け、カリーナが素っ頓狂な声を上げた。
白髪の女性のほうを見ると、彼女は特に取り乱すこともなく、涼しげな表情をしたままだ。
マリアと彼女のどちらが美人か……主観が入る分、どちらとも答えづらい問題だ。
俺からすれば、ほとんど違いはないように感じるが……
「解答します。私の容姿は神機使用者の思考と、マリアのイメージで形成されました」
「……なんだって?」
不味い反応をしてしまった。
すぐに取り繕うが、すでにドロシーたちは眉をひそめてこちらを見ていた。
「隊長補佐、どうしたのさ?」
黙っているとかえって怪しまれる。
そう思った俺は、素直に彼女の言葉を繰り返した。
「その……彼女の見た目は、俺の思考と、俺の知るマリアのイメージから生まれたらしい」
「うん? 難しいことは分かんないけどさ……それって、あんたの好みが反映されてるってことか?」
「……っ!」
「ま、ま、ま、まさか……見えないのをいいことに、ドセクシーな姿をしているとか!?」
カリーナは慌てた様子で、顔を赤くさせている。
「これはドセクシー、というものですか?」
さらに白髪の女性からそう尋ねられて、俺は頭が痛くなった気がした。
それから改めて、女性の姿を頭から足先まで確認してみる。
黒と白の清楚なドレス、金色に輝く茨が絡みついた白い首筋やすらりと伸びた足。
セクシーと言われれば、そうなのかもしれない。
しかし、それでもはっきりと宣言させてもらいたい。
「……その姿は、ドセクシーではないと思う」
誓って嘘ではない。
容姿のベースが見慣れた人物であるせいか、色気というものは感じない。
元のマリアより薄着に見えるのも、おそらく俺の気のせいだろう。
「そ、そうですかっ! いろいろ想像しちゃったじゃないですか……もう」
カリーナは赤い顔を冷ますように、両手をパタパタと扇ぐ。
そうしていると、レイラが大きく咳払いをした。
「……あの。まだ、この話を続けますか?」
彼女は不機嫌そうに眉をひそめる。……だから、どうして俺を睨むんだ。
「おっと、お姫様がお怒りだ。この話は置いといて……次の質問!」
言いながらドロシーが大きく挙手する。
「アラガミって、美味いのか?」
名前を呼ぶと、ドロシーはあっけらかんとした表情で言った。
俺とレイラ、それに白髪の女性の間にしばし沈黙が流れる。
「……」
「それ私も気になってました! アラガミを捕喰した時って、味とかあるんでしょうか?」
しかしそこで、興味津々と言った様子でカリーナが更に手を挙げた。
これが女子会のノリというヤツなのだろうか……
何故そんな質問をする必要があるのか。理解の及ばない展開が続く。
「アラガミの味……? 偏食傾向のことでしょうか?」
「……質問の意図を測りかねているようです」
「それはそうでしょうね……」
「いやー、あたしらはアラガミなんて食べれないからさ、どんな味がするのか気になるんだよ。もしかしたら、種類ごとに、違う味がしたりしてな」
ドロシーは例えば、と言葉を続ける。
「シユウはチキンの味とか、ドレッドパイクは虫の味とか、チェルノボグも虫の味で、コクーンメイデンも……」
「虫ばっかりじゃない!」
カリーナがキレのあるツッコミを見せる。
「あはは、さすがに美味そうなアラガミは思いつかないな……。で、味はともかく、アラガミを捕喰する感覚って、どうなんだろうな?」
「……感覚、ですか」
ドロシーの質問に戸惑っているのか、白髪の女性は言葉を濁らせた。
そんな彼女の表情を見たのは、これで二回目。
マリアの墓前で、心について考えていた時も、彼女は戸惑っているように見えた。
「……こういう類の話は、答えにくいみたいだ」
「う~ん。まぁ、あたしたちは神機の感覚が分からないし、人間目線の話をするのも酷だったかもな」
仕方がないと、ドロシーは残念そうな表情を浮かべた。
そうしていると、寡黙的な態度を貫いていたレイラが大きな溜息をつく。
「まったく……。品のない話が続きますね」
「気にしたら負けだって! 姫様的には何か訊きたいことはないのかい?」
ドロシーの問いを聞くと、レイラは思慮深い瞳を向ける。
「そうですね……。わたくしは、彼女が何者なのか知りたいです」
「何者なのか……」
皆が敢えてしなかった質問を、レイラは躊躇なく口にする。
先ほどまでの質問とは打って変わり、かなり踏み入った内容だ。
「んー、声の主さんは声の主さん、じゃ駄目なのかい?」
「私が訊きたいのは、もっと根本的なことです。彼女は生物なのか、機械的なものなのか」
レイラは一度言葉を止め、絞り出すようにして続きを口にした。
「それとも……霊的なものなのか」
俺はレイラから、白髪の女性に視線を移す。
彼女は表情を崩さないまま、事務的に言葉を紡ぎ出した。
「何者かという問いについては、神機に捕喰された八神マリアから生じた何か、となります。生物であるか、機械であるか、私が回答できる情報群の中には、正解がないと思っていただいてよろしいかと」
彼女の正体は、彼女自身にもよく分からないということか。
その言葉を聞いて俺は、落胆したような、ホッとしたような気持ちになった。
「……それって、結局よー分からん! ってことかい?」
彼女の言葉をそのまま伝えると、ドロシーは困惑交じりにそう言った。
「うーん、そういうものなのかもしれませんよ。人間だって周りの情報から、あなたは人間ですって教えられなければ、自分が何者かなんて……ねえ?」
「……であるならば、意外と機械ではなく生物に近いのかもしれません」
レイラは金髪をかきあげ、視線を逸らした。
「そうですよね。もし機械に近いのなら、アビスファクターのように取り扱い方の説明が付いてそうですしね」
確かに、具体的に自分の性能を語れる人間など存在しないだろう。
人は常に変化し、成長していく。だから彼女も曖昧なのだと考えれば、納得もいく。
そこでドロシーが「ちょっと待った」と口を挟んだ。
「ていうか、神機ってのは普通、説明書がついているのかい?」
「いえ、ほぼ使って覚えろ、です」
「適当だな、おい!?」
即答するレイラに対し、ドロシーは呆れたように脱力する。
「そんなアバウトでいいのかよ……危険物なのにさ」
「まぁ、説明書一つで安全に使えるほど、神機は易しいものではありませんし」
レイラは俺に同意を求めるように、「そうですよね?」と尋ねてくる。
俺は軽く頷き、レイラの言葉に続ける。
「神機がなければ人は生き残れない。だから俺は、神機を使っています」
「……やっぱ適当じゃん!」
ドロシーは叫び、レイラは深くため息を吐く。
真面目に答えたつもりだったのだが……
「あんたら、本当タフだよな……そんなよく分からないもの使ってさ」
「じゃあ、よく分からない、ということも含めて……つまり、彼女は神機的な何かってことなんでしょうか?」
「……そうなのか?」
俺が白い女性に視線を移すと、カリーナやレイラも釣られて彼女がいる場所に顔を向ける。
彼女は質問に答えるべく、薄い唇を開いた。
「不明です」
返答はあっさりしていた。
そのあともずっと話は続いたが、マリアに似た彼女の正体を掴む、有力な情報は出てこなかった。
不明。
その言葉が全てを表しているかのように、俺たちにとって彼女は未知の存在のままだった。
話を一通り終え、解散した後。
俺はゴドーの任務を手伝って、ネブカドネザルを探すために支部を出ていた。
同時に支部に向かっていきそうなアラガミはなるべくこちらで駆除しておく。
先ほど会話をしている間も、レイラは少し疲れを見せていた。
こんなことで巡回討伐の負担が減るとも思えないが、何事も積み重ねだろう。
そうして探索を行っていると、いつからかそこにいる白髪の女性が、物言いたげな視線を俺に向けていた。
「何か気になることでもあるのか?」
「はい」
「まさか……ネブカドネザルを発見したのか?」
「いえ、違います」
あっさり否定され、肩透かしを食らった思いがしたが……気持ちを切り替えて尋ねる。
「では、何が気になっているんだ?」
「それは……」
白髪の女性は考え込むような間を作った後で、俺の目を見る。
「先ほどのトークパーティというものは、何だったのでしょうか?」
「何だった、か……」
「質疑応答の場にしては、内容がなかった気がします」
……何とも答えづらい質問だ。
確かに目に見えた収穫は少なかったが、主賓から内容がないと言い切られるのも寂しいものがある。
「あれはあれで、有意義だったんじゃないか」
俺は素直な気持ちでそう答える。
カリーナたちにはマリアの死と、マリアによく似た隣人を受け入れるための時間が必要だった。
付き合わされた側の彼女からすれば、理解しにくいことだろうが……
心の整理をつけるためには、必要な手順を踏む必要がある。
機械的に済ませることができないものだということは、最近俺も実感したばかりだ。
「では、やはり意味があったと?」
「いや、あの会話自体には、そう意味はないんだが……」
「意味がないことに意味があったと? 理解が難しいです」
難しいと言いつつも、彼女の表情は変わらない。
声も抑揚がなく、感情を読み取る術がない。
この表情の裏側に感情と呼べるものがあるのか、それとも俺が感傷でそれを見出そうとしているだけなのか……答えは出ない。
「ただ、彼女たちの会話は参考になりました。あのような会話を継続できるのが、女性なのですね」
「……知らなかったのか?」
「はい」
彼女は当たり前に頷いてみせる。
マリアによく似た彼女だが、やはり彼女は知らないのだ。カリーナたちとどのように会話していたのか、覚えていない。
いや……初めからそんな経験をしたことがないのか。
「……あんな風に話すのは、女性に限ったことではないんだ。男性でも、親しい間柄なら意味もなく話し続けられる」
「そうなのですか? ですが、あなたがそうしている姿はほとんど見たことがありません」
「それは……俺にそういう相手がいないだけだ」
答えていて虚しくなるが、そんなことを気にしてくれる相手ではない。
その後も彼女は俺の痛いところに土足で踏み込み、無秩序に蹂躙し続けた。
そんな中でふと、思い至る。
意味があるけど、意味のない会話……それを今、俺と彼女は実践している。
会話の経験がないと、何となく続く会話というのは意味が分からないものらしいが……
だったら、これから経験を積んでいけばどうなるのか。
「…………」
アラガミを発見するまで、彼女との取り留めのない雑談は続けられた。
『ミッション終了です! お疲れ様でした!』
戦闘終了後、カリーナの通信が入る。俺はその声を聞き、神機を収めた。
遭遇したのは小型種を中心にしたアラガミの群れだった、消耗はかなり少ない。
「疲れていないのに、お疲れ様と言われるのですね」
姿を現した白髪の女性は、そう俺に問う。
「いつものことだろう?」
「なるほど、慣例事項ということですね。これが挨拶、というものでしょうか」
相変わらず、彼女は表情一つ崩さない。だが、その口振りはいつもより軽いものに感じる。
こんなことが、今まであっただろうか。
「……何かあったのか?」
白髪の女性が軽く頷く。
「八神マリアの形見の指輪を、あなたが神機に捕喰させたことを覚えていますか?」
「ああ、覚えている」
あの時、俺はマリアに贈った指輪を神機に捕喰させた。
家族の証が、せめてマリアの傍にあるようにと。
それに対し、彼女は俺の行動意図が分からないと無機質に語るばかりだった。
「指輪を捕喰させるのは、無意味ではないか。そう私が尋ねた時、レイラが言いました――意味があるかどうかは、心が決めるのよ、と」
「…………」
「この一言が、繰り返されるのです。何度も、何度も……」
白髪の女性は、俺のほうをじっと見つめる。マリアに似た顔で、瞳で。
「心とは、何なのでしょうか」
そう問う姿は、いつもの無機質な彼女ではない。
(彼女は、何かが変わりつつあるのか……?)
その違和感を言葉にできず、俺は彼女の問いに答えられなかった。
産業棟を歩いていると、正面から歩いてきたゴドーと鉢合わせる。
何かを買ってきた帰りらしく、その手には、折りたたまれた茶色い小さな紙袋を持っている。
「どうかしたのか?」
産業棟でゴドーと会うのは珍しいが、彼の関心はむしろ俺のほうにあるようだった。
「なるほど……心とは何なのか、か。君がそれをうまく説明できなかったと」
「はい」
ゴドーは俺の話を聞きながら、壁に背中を預けて腕を組んだ。
「ま、いきなり訊かれて即答できる者もそうはいない。俺だってよく分からんと答えただろう」
ゴドーはそう言って薄く笑った。
「しかし、面白い変化だな。意味のなさそうな会話に関心を持ち、心とは何かを知りたがる、か……」
「今までに、そのような素振りはありませんでした」
「なるほど……」
ゴドーは一度、考えるように口元に手を当てたが、すぐに俺のほうへ向き直る。
「そうだな……やってみるか」
そうして今度はサングラスを指で押し上げながら、不敵な笑みを浮かべてみせた。
「君は何でもいいから、彼女に刺激を与えてみてくれ」
「……何でも?」
「言葉や感覚を通して、俺たちが見ているもの、感じているものを教えてやるんだ。例えるなら……本やデータからの情報を与えるとか、好奇心旺盛な子供の知識欲を満たしてやるような感じだ」
「それが、『刺激』ですか」
「ああ。なるべく彼女が知らなそうなことがいい」
ゴドーはニヤリと口角を上げる。
「君が与える刺激は、彼女に変化を与えるだけではなく、彼女のことを知るためにも役立つだろう」
「なるほど……」
彼女が自分のことを知らないのであれば、それを言語化するために必要なことを教えればいい。
『アビスファクター』はこの支部を守るために必要な力だ。知っておいて困ることもないだろう。
しかし、ゴドーはそのことより、むしろ彼女の変化に興味を持っているように見えた。
単なる興味本位なのだろうか。それとも他に、意図があるのか……
「頼んだぞ、セイ」
軽く言ったゴドーの考えは読み取れない。分厚いサングラス越しでは、その表情の意味を理解することも難しい。
以前にゴドーが、彼女と親しげに会話していたことを思い出す。彼は誰よりも早く、彼女を人間的に捉えていたように思う。
ゴドーは彼女のことをどう見ていて、どうあって欲しいと思っているのだろう。
(……余計なことを考え過ぎだ)
軽く頭を振り、無意味な思考を打ち消した。ゴドーは実力ある指揮官であり、信頼できる戦友だ。
マリアがその背中を預けてきた相手でもある。……疑う必要はない。
俺はただ、彼が必要だと思うことを実行していけばいいはずだ。
冷たい壁に囲まれた中にある、大型の機械。機械には、円形のモニターが嵌められ、画面からは淡い光が放たれている。
その機械――ゴッドイーターや神機、アラガミ、オラクル細胞……フェンリルが今まで集めてきたあらゆる情報を閲覧することができる情報端末、『ターミナル』を白髪の女性に見せながら、俺は自分の知っていることを話して聞かせた。
「神機のことは知っているか?」
「はい。第一世代型の神機、もっと古いピストル型神機のことも知っています」
俺はターミナルに付属されている文字盤を操作し、別の画面を開く。
「ゴッドイーターの歴史、これも分かります。アラガミも一般的な種類は知っています」
基本的な知識は持っているのか、座学で習うようなことは何でもすんなり答えてみせる。
「これも知っています。ヒマラヤ支部のこと、人間のこと、あなたのことも」
「……そうか」
彼女が言う、知っているとはどれくらいのことなのか。それを詳しく尋ねることは躊躇われた。
その後も支部のデータや個人の基礎情報を開示していったが、彼女に変化はなかった。
分かったのは、俺が考えていた以上に彼女は様々なことを知っていたということくらいか。
別の画面に移ろうとしたとき、彼女がふと口を開いた。
「これは、知らないです」
彼女は画面に映された、ある情報を指さした。
「……ロシア支部のデータか。ここはクロエ支部長の出身地だ」
「クロエ支部長? その方はいったい誰でしょうか」
彼女は大きな瞳を俺に向ける。
「誰って……。ポルトロン元支部長の代わりに来た、新支部長だろ?」
「なるほど、記憶しました」
言われてみれば、神機を持った状態でクロエと話したことはない。知らなくて当然のことだろう。
どうやら彼女は、データベースのような膨大な情報リソースを持っている訳ではないらしい。
それどころか、むしろ人に近い。知識量レベルとしては、勉強熱心な一人の人間くらいだ。
(……マリアと同じくらい、か?)
彼女が持つ知識の基礎は、マリアのものであった可能性が高そうだ。
会話などの知識は持っておらず、神機やアラガミについての知識ばかり記憶しているのは、彼女が神機と深くつながっているためだろうか。
ふと、マリアに座学を教えてもらったことを思い出す。
彼女は幼い頃から、とても真面目な人間だったが……
その頃の記憶も、彼女の中に情報として蓄えられてはいないのだろうか。
今は思い出せないだけで、もしかしたら……
「あの、どうかしましたか?」
マリアの声で、マリアでない何者かが話しかけてくる。
「いや……なんでもない」
彼女は俺の知っている人物ではない。
そう頭では考えつつも、どうしても彼女の姿がマリアの姿と重なってしまう。
俺は、彼女にどうなって欲しいのだろうか。
刺激を与えて、変化を促して、彼女が何になるというのだろう。
八神マリアは死んだ。
そのことはすでに理解したし、折り合いもつけたはずだ。
マリアの代替品を求めるようなつもりはない。そんなものは、誰のためにも望むべきではない。
だが、それでも彼女はマリアに似過ぎている。
目の前の女性とどう接すればいいか、俺はだんだん分からなくなってきていた。
「よーし、呼んでくれていいぞ、セイ!」
ドロシーが弾んだ声で、俺にゴーサインを出す。
「どの辺ですか? この辺? この辺に出ます?」
「はぁ……どこに出ても同じでしょう。わたくしたちには見えないのですから」
楽しげなカリーナたちの様子に対して、レイラは冷静な姿勢を崩さない。
俺はそんな彼女たちの声を聞きつつ、神機に触れて目を閉じた。
心の中で彼女に呼びかけると、白い髪をなびかせた女性がふわりと目の前に現れる。
姿を現した彼女は、無機質な瞳をこちらに向けた。
「お呼びでしょうか」
「ああ……。彼女たちたっての希望でな」
「彼女たち……?」
首を傾げた純白の女性に対し、俺は視線でレイラたちを見るよう促した。
興味深そうにこちらを見ていたカリーナが口を開く。
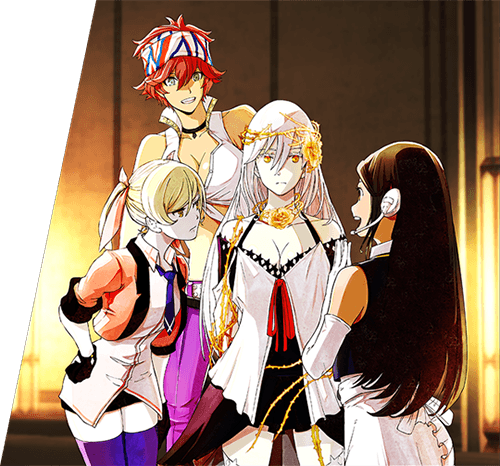 「八神さん、今声の主さんがいるんですね?」
「八神さん、今声の主さんがいるんですね?」「はい。俺のすぐ隣に立っています」
「ほ、本当ですか? わー、全然分からないです」
じっと目を凝らすカリーナの隣で、レイラは澄ました顔で腕を組んでいる。
「見えず聞こえず、触れず、です。その方は、隊長補佐を介してしか、言葉のやり取りができませんよ」
すでに似たような場面を何度も経験しているためか、レイラは他二人に比べれば落ち着いている。
しかし興味がない訳ではないようで、カリーナたちが囲んだその場所へ流し目を向けている。
「幽霊ってのが本当にいたら、こんな感じなんだろうな。なぁ、声の主さんは憑りついたり、呪ったりはしないのか?」
「そのような機能はありません」
ドロシーの質問に対し、白髪の女性が即座に答える。
「それってつまり……機能があれば呪ったってこと?」
「必要があれば」
「……そこまでにしなさい。その手の話は不愉快よ」
彼女の言葉をそのまま伝えていると、レイラにきつく睨まれた。
質問も返答も、俺のものではないのだが……
「そっかそっか、レイラはこういう話が苦手なんだっけ?」
「なっ……苦手ではありません。くだらないと言っているだけです」
「まあまあ……オカルトじみた話はともかく、特にイヤな気配とかもないですし、安全、ということでいいんですよね?」
「……はい。問題ないと思います」
少なくとも、彼女が俺に危害を加えたことは一度もない。
しかし、どうしてそんなことを尋ねるのだろう。
「結局、ご用件はなんなのでしょうか」
「……分からない」
それは俺も聞きたいところだった。
ドロシーに捕まり、神機を持って来いと言われ、なし崩し的に彼女を呼び出すことになった。
盛り上がる女性陣を前に、なんとなく居心地の悪さを感じていると、不意にドロシーがこちらを向いて宣言した。
「よーし! じゃ、マリア声の主さんを交えた、トークパーティの始まりだぜ!」
「わー! よろしくお願いしまーす!」
「トークパーティ……ですか?」
俺との声がぴたりと重なる。
トークパーティ……つまりは一般に女子会、ガールズトークと呼称されるものの類だろうか。
つまり俺は、ドロシーが言うところの『マリア声の主さん』の召喚と通訳のためにここに呼び出されたらしい。
……十中八九、必要がなければ一生縁のなかった場面だろう。
(一体、どんな話をすればいいんだ? ……いや、主賓じゃないから黙っていればいいのか)
とはいえ隣に立つ無表情な彼女が、楽しくトークパーティする姿も想像がつかない。
パチパチと拍手をするカリーナの隣で、レイラが深い溜息をつく。
「成立するのかしら、これ……」
「成立するんじゃない。成立させるんだよ、隊長補佐がな!」
ドロシーの腕がぐっと伸び、強引に俺の肩に回された。
俺が成立させるのか? 司会進行やトークスキルの低さは、周知の事実だと思うのだが……
そうして悩んでいると、それを察してか彼女が声をかけてくる。
「私は何をすればいいのでしょうか?」
「……そうだな、彼女たちの質問に答えてあげてくれ」
「分かりました」
苦し紛れにそう言うと、女性はすんなり頷いてくれた。
丸投げするようで申し訳ないが、俺一人ではこの場を乗り切ることは不可能だ。
……それにしても彼女は、その姿こそマリアに近いが、どこまでも俺の言葉に従順だ。
(マリアなら、すんなり協力はしてくれなかっただろうな……)
きっと成長を促すために、率先して俺が場を仕切るように仕向けただろう。
この女性はマリアとは違い、俺の言うことに逆らわない。
だからこそ浮き彫りになる。やはり彼女は、俺の家族とは別人なのだと。
「じゃあ、質問がある人から順番にどうぞ」
俺がそう言うと、真っ先にドロシーが手を挙げた。
「はいはい! まず、これは訊きたかったんだけどさ、声の主さんとマリアって、どっちが美人さんなの?」
「えっ、いきなりそこ!?」
真剣な表情で尋ねるドロシーに向け、カリーナが素っ頓狂な声を上げた。
白髪の女性のほうを見ると、彼女は特に取り乱すこともなく、涼しげな表情をしたままだ。
マリアと彼女のどちらが美人か……主観が入る分、どちらとも答えづらい問題だ。
俺からすれば、ほとんど違いはないように感じるが……
「解答します。私の容姿は神機使用者の思考と、マリアのイメージで形成されました」
「……なんだって?」
不味い反応をしてしまった。
すぐに取り繕うが、すでにドロシーたちは眉をひそめてこちらを見ていた。
「隊長補佐、どうしたのさ?」
黙っているとかえって怪しまれる。
そう思った俺は、素直に彼女の言葉を繰り返した。
「その……彼女の見た目は、俺の思考と、俺の知るマリアのイメージから生まれたらしい」
「うん? 難しいことは分かんないけどさ……それって、あんたの好みが反映されてるってことか?」
「……っ!」
「ま、ま、ま、まさか……見えないのをいいことに、ドセクシーな姿をしているとか!?」
カリーナは慌てた様子で、顔を赤くさせている。
「これはドセクシー、というものですか?」
さらに白髪の女性からそう尋ねられて、俺は頭が痛くなった気がした。
それから改めて、女性の姿を頭から足先まで確認してみる。
黒と白の清楚なドレス、金色に輝く茨が絡みついた白い首筋やすらりと伸びた足。
セクシーと言われれば、そうなのかもしれない。
しかし、それでもはっきりと宣言させてもらいたい。
「……その姿は、ドセクシーではないと思う」
誓って嘘ではない。
容姿のベースが見慣れた人物であるせいか、色気というものは感じない。
元のマリアより薄着に見えるのも、おそらく俺の気のせいだろう。
「そ、そうですかっ! いろいろ想像しちゃったじゃないですか……もう」
カリーナは赤い顔を冷ますように、両手をパタパタと扇ぐ。
そうしていると、レイラが大きく咳払いをした。
「……あの。まだ、この話を続けますか?」
彼女は不機嫌そうに眉をひそめる。……だから、どうして俺を睨むんだ。
「おっと、お姫様がお怒りだ。この話は置いといて……次の質問!」
言いながらドロシーが大きく挙手する。
「アラガミって、美味いのか?」
名前を呼ぶと、ドロシーはあっけらかんとした表情で言った。
俺とレイラ、それに白髪の女性の間にしばし沈黙が流れる。
「……」
「それ私も気になってました! アラガミを捕喰した時って、味とかあるんでしょうか?」
しかしそこで、興味津々と言った様子でカリーナが更に手を挙げた。
これが女子会のノリというヤツなのだろうか……
何故そんな質問をする必要があるのか。理解の及ばない展開が続く。
「アラガミの味……? 偏食傾向のことでしょうか?」
「……質問の意図を測りかねているようです」
「それはそうでしょうね……」
「いやー、あたしらはアラガミなんて食べれないからさ、どんな味がするのか気になるんだよ。もしかしたら、種類ごとに、違う味がしたりしてな」
ドロシーは例えば、と言葉を続ける。
「シユウはチキンの味とか、ドレッドパイクは虫の味とか、チェルノボグも虫の味で、コクーンメイデンも……」
「虫ばっかりじゃない!」
カリーナがキレのあるツッコミを見せる。
「あはは、さすがに美味そうなアラガミは思いつかないな……。で、味はともかく、アラガミを捕喰する感覚って、どうなんだろうな?」
「……感覚、ですか」
ドロシーの質問に戸惑っているのか、白髪の女性は言葉を濁らせた。
そんな彼女の表情を見たのは、これで二回目。
マリアの墓前で、心について考えていた時も、彼女は戸惑っているように見えた。
「……こういう類の話は、答えにくいみたいだ」
「う~ん。まぁ、あたしたちは神機の感覚が分からないし、人間目線の話をするのも酷だったかもな」
仕方がないと、ドロシーは残念そうな表情を浮かべた。
そうしていると、寡黙的な態度を貫いていたレイラが大きな溜息をつく。
「まったく……。品のない話が続きますね」
「気にしたら負けだって! 姫様的には何か訊きたいことはないのかい?」
ドロシーの問いを聞くと、レイラは思慮深い瞳を向ける。
「そうですね……。わたくしは、彼女が何者なのか知りたいです」
「何者なのか……」
皆が敢えてしなかった質問を、レイラは躊躇なく口にする。
先ほどまでの質問とは打って変わり、かなり踏み入った内容だ。
「んー、声の主さんは声の主さん、じゃ駄目なのかい?」
「私が訊きたいのは、もっと根本的なことです。彼女は生物なのか、機械的なものなのか」
レイラは一度言葉を止め、絞り出すようにして続きを口にした。
「それとも……霊的なものなのか」
俺はレイラから、白髪の女性に視線を移す。
彼女は表情を崩さないまま、事務的に言葉を紡ぎ出した。
「何者かという問いについては、神機に捕喰された八神マリアから生じた何か、となります。生物であるか、機械であるか、私が回答できる情報群の中には、正解がないと思っていただいてよろしいかと」
彼女の正体は、彼女自身にもよく分からないということか。
その言葉を聞いて俺は、落胆したような、ホッとしたような気持ちになった。
「……それって、結局よー分からん! ってことかい?」
彼女の言葉をそのまま伝えると、ドロシーは困惑交じりにそう言った。
「うーん、そういうものなのかもしれませんよ。人間だって周りの情報から、あなたは人間ですって教えられなければ、自分が何者かなんて……ねえ?」
「……であるならば、意外と機械ではなく生物に近いのかもしれません」
レイラは金髪をかきあげ、視線を逸らした。
「そうですよね。もし機械に近いのなら、アビスファクターのように取り扱い方の説明が付いてそうですしね」
確かに、具体的に自分の性能を語れる人間など存在しないだろう。
人は常に変化し、成長していく。だから彼女も曖昧なのだと考えれば、納得もいく。
そこでドロシーが「ちょっと待った」と口を挟んだ。
「ていうか、神機ってのは普通、説明書がついているのかい?」
「いえ、ほぼ使って覚えろ、です」
「適当だな、おい!?」
即答するレイラに対し、ドロシーは呆れたように脱力する。
「そんなアバウトでいいのかよ……危険物なのにさ」
「まぁ、説明書一つで安全に使えるほど、神機は易しいものではありませんし」
レイラは俺に同意を求めるように、「そうですよね?」と尋ねてくる。
俺は軽く頷き、レイラの言葉に続ける。
「神機がなければ人は生き残れない。だから俺は、神機を使っています」
「……やっぱ適当じゃん!」
ドロシーは叫び、レイラは深くため息を吐く。
真面目に答えたつもりだったのだが……
「あんたら、本当タフだよな……そんなよく分からないもの使ってさ」
「じゃあ、よく分からない、ということも含めて……つまり、彼女は神機的な何かってことなんでしょうか?」
「……そうなのか?」
俺が白い女性に視線を移すと、カリーナやレイラも釣られて彼女がいる場所に顔を向ける。
彼女は質問に答えるべく、薄い唇を開いた。
「不明です」
返答はあっさりしていた。
そのあともずっと話は続いたが、マリアに似た彼女の正体を掴む、有力な情報は出てこなかった。
不明。
その言葉が全てを表しているかのように、俺たちにとって彼女は未知の存在のままだった。
話を一通り終え、解散した後。
俺はゴドーの任務を手伝って、ネブカドネザルを探すために支部を出ていた。
同時に支部に向かっていきそうなアラガミはなるべくこちらで駆除しておく。
先ほど会話をしている間も、レイラは少し疲れを見せていた。
こんなことで巡回討伐の負担が減るとも思えないが、何事も積み重ねだろう。
そうして探索を行っていると、いつからかそこにいる白髪の女性が、物言いたげな視線を俺に向けていた。
「何か気になることでもあるのか?」
「はい」
「まさか……ネブカドネザルを発見したのか?」
「いえ、違います」
あっさり否定され、肩透かしを食らった思いがしたが……気持ちを切り替えて尋ねる。
「では、何が気になっているんだ?」
「それは……」
白髪の女性は考え込むような間を作った後で、俺の目を見る。
「先ほどのトークパーティというものは、何だったのでしょうか?」
「何だった、か……」
「質疑応答の場にしては、内容がなかった気がします」
……何とも答えづらい質問だ。
確かに目に見えた収穫は少なかったが、主賓から内容がないと言い切られるのも寂しいものがある。
「あれはあれで、有意義だったんじゃないか」
俺は素直な気持ちでそう答える。
カリーナたちにはマリアの死と、マリアによく似た隣人を受け入れるための時間が必要だった。
付き合わされた側の彼女からすれば、理解しにくいことだろうが……
心の整理をつけるためには、必要な手順を踏む必要がある。
機械的に済ませることができないものだということは、最近俺も実感したばかりだ。
「では、やはり意味があったと?」
「いや、あの会話自体には、そう意味はないんだが……」
「意味がないことに意味があったと? 理解が難しいです」
難しいと言いつつも、彼女の表情は変わらない。
声も抑揚がなく、感情を読み取る術がない。
この表情の裏側に感情と呼べるものがあるのか、それとも俺が感傷でそれを見出そうとしているだけなのか……答えは出ない。
「ただ、彼女たちの会話は参考になりました。あのような会話を継続できるのが、女性なのですね」
「……知らなかったのか?」
「はい」
彼女は当たり前に頷いてみせる。
マリアによく似た彼女だが、やはり彼女は知らないのだ。カリーナたちとどのように会話していたのか、覚えていない。
いや……初めからそんな経験をしたことがないのか。
「……あんな風に話すのは、女性に限ったことではないんだ。男性でも、親しい間柄なら意味もなく話し続けられる」
「そうなのですか? ですが、あなたがそうしている姿はほとんど見たことがありません」
「それは……俺にそういう相手がいないだけだ」
答えていて虚しくなるが、そんなことを気にしてくれる相手ではない。
その後も彼女は俺の痛いところに土足で踏み込み、無秩序に蹂躙し続けた。
そんな中でふと、思い至る。
意味があるけど、意味のない会話……それを今、俺と彼女は実践している。
会話の経験がないと、何となく続く会話というのは意味が分からないものらしいが……
だったら、これから経験を積んでいけばどうなるのか。
「…………」
アラガミを発見するまで、彼女との取り留めのない雑談は続けられた。
『ミッション終了です! お疲れ様でした!』
戦闘終了後、カリーナの通信が入る。俺はその声を聞き、神機を収めた。
遭遇したのは小型種を中心にしたアラガミの群れだった、消耗はかなり少ない。
「疲れていないのに、お疲れ様と言われるのですね」
姿を現した白髪の女性は、そう俺に問う。
「いつものことだろう?」
「なるほど、慣例事項ということですね。これが挨拶、というものでしょうか」
相変わらず、彼女は表情一つ崩さない。だが、その口振りはいつもより軽いものに感じる。
こんなことが、今まであっただろうか。
「……何かあったのか?」
白髪の女性が軽く頷く。
「八神マリアの形見の指輪を、あなたが神機に捕喰させたことを覚えていますか?」
「ああ、覚えている」
あの時、俺はマリアに贈った指輪を神機に捕喰させた。
家族の証が、せめてマリアの傍にあるようにと。
それに対し、彼女は俺の行動意図が分からないと無機質に語るばかりだった。
「指輪を捕喰させるのは、無意味ではないか。そう私が尋ねた時、レイラが言いました――意味があるかどうかは、心が決めるのよ、と」
「…………」
「この一言が、繰り返されるのです。何度も、何度も……」
白髪の女性は、俺のほうをじっと見つめる。マリアに似た顔で、瞳で。
「心とは、何なのでしょうか」
そう問う姿は、いつもの無機質な彼女ではない。
(彼女は、何かが変わりつつあるのか……?)
その違和感を言葉にできず、俺は彼女の問いに答えられなかった。
産業棟を歩いていると、正面から歩いてきたゴドーと鉢合わせる。
何かを買ってきた帰りらしく、その手には、折りたたまれた茶色い小さな紙袋を持っている。
「どうかしたのか?」
産業棟でゴドーと会うのは珍しいが、彼の関心はむしろ俺のほうにあるようだった。
「なるほど……心とは何なのか、か。君がそれをうまく説明できなかったと」
「はい」
ゴドーは俺の話を聞きながら、壁に背中を預けて腕を組んだ。
「ま、いきなり訊かれて即答できる者もそうはいない。俺だってよく分からんと答えただろう」
ゴドーはそう言って薄く笑った。
「しかし、面白い変化だな。意味のなさそうな会話に関心を持ち、心とは何かを知りたがる、か……」
「今までに、そのような素振りはありませんでした」
「なるほど……」
ゴドーは一度、考えるように口元に手を当てたが、すぐに俺のほうへ向き直る。
「そうだな……やってみるか」
そうして今度はサングラスを指で押し上げながら、不敵な笑みを浮かべてみせた。
「君は何でもいいから、彼女に刺激を与えてみてくれ」
「……何でも?」
「言葉や感覚を通して、俺たちが見ているもの、感じているものを教えてやるんだ。例えるなら……本やデータからの情報を与えるとか、好奇心旺盛な子供の知識欲を満たしてやるような感じだ」
「それが、『刺激』ですか」
「ああ。なるべく彼女が知らなそうなことがいい」
ゴドーはニヤリと口角を上げる。
「君が与える刺激は、彼女に変化を与えるだけではなく、彼女のことを知るためにも役立つだろう」
「なるほど……」
彼女が自分のことを知らないのであれば、それを言語化するために必要なことを教えればいい。
『アビスファクター』はこの支部を守るために必要な力だ。知っておいて困ることもないだろう。
しかし、ゴドーはそのことより、むしろ彼女の変化に興味を持っているように見えた。
単なる興味本位なのだろうか。それとも他に、意図があるのか……
「頼んだぞ、セイ」
軽く言ったゴドーの考えは読み取れない。分厚いサングラス越しでは、その表情の意味を理解することも難しい。
以前にゴドーが、彼女と親しげに会話していたことを思い出す。彼は誰よりも早く、彼女を人間的に捉えていたように思う。
ゴドーは彼女のことをどう見ていて、どうあって欲しいと思っているのだろう。
(……余計なことを考え過ぎだ)
軽く頭を振り、無意味な思考を打ち消した。ゴドーは実力ある指揮官であり、信頼できる戦友だ。
マリアがその背中を預けてきた相手でもある。……疑う必要はない。
俺はただ、彼が必要だと思うことを実行していけばいいはずだ。
冷たい壁に囲まれた中にある、大型の機械。機械には、円形のモニターが嵌められ、画面からは淡い光が放たれている。
その機械――ゴッドイーターや神機、アラガミ、オラクル細胞……フェンリルが今まで集めてきたあらゆる情報を閲覧することができる情報端末、『ターミナル』を白髪の女性に見せながら、俺は自分の知っていることを話して聞かせた。
「神機のことは知っているか?」
「はい。第一世代型の神機、もっと古いピストル型神機のことも知っています」
俺はターミナルに付属されている文字盤を操作し、別の画面を開く。
「ゴッドイーターの歴史、これも分かります。アラガミも一般的な種類は知っています」
基本的な知識は持っているのか、座学で習うようなことは何でもすんなり答えてみせる。
「これも知っています。ヒマラヤ支部のこと、人間のこと、あなたのことも」
「……そうか」
彼女が言う、知っているとはどれくらいのことなのか。それを詳しく尋ねることは躊躇われた。
その後も支部のデータや個人の基礎情報を開示していったが、彼女に変化はなかった。
分かったのは、俺が考えていた以上に彼女は様々なことを知っていたということくらいか。
別の画面に移ろうとしたとき、彼女がふと口を開いた。
「これは、知らないです」
彼女は画面に映された、ある情報を指さした。
「……ロシア支部のデータか。ここはクロエ支部長の出身地だ」
「クロエ支部長? その方はいったい誰でしょうか」
彼女は大きな瞳を俺に向ける。
「誰って……。ポルトロン元支部長の代わりに来た、新支部長だろ?」
「なるほど、記憶しました」
言われてみれば、神機を持った状態でクロエと話したことはない。知らなくて当然のことだろう。
どうやら彼女は、データベースのような膨大な情報リソースを持っている訳ではないらしい。
それどころか、むしろ人に近い。知識量レベルとしては、勉強熱心な一人の人間くらいだ。
(……マリアと同じくらい、か?)
彼女が持つ知識の基礎は、マリアのものであった可能性が高そうだ。
会話などの知識は持っておらず、神機やアラガミについての知識ばかり記憶しているのは、彼女が神機と深くつながっているためだろうか。
ふと、マリアに座学を教えてもらったことを思い出す。
彼女は幼い頃から、とても真面目な人間だったが……
その頃の記憶も、彼女の中に情報として蓄えられてはいないのだろうか。
今は思い出せないだけで、もしかしたら……
「あの、どうかしましたか?」
マリアの声で、マリアでない何者かが話しかけてくる。
「いや……なんでもない」
彼女は俺の知っている人物ではない。
そう頭では考えつつも、どうしても彼女の姿がマリアの姿と重なってしまう。
俺は、彼女にどうなって欲しいのだろうか。
刺激を与えて、変化を促して、彼女が何になるというのだろう。
八神マリアは死んだ。
そのことはすでに理解したし、折り合いもつけたはずだ。
マリアの代替品を求めるようなつもりはない。そんなものは、誰のためにも望むべきではない。
だが、それでも彼女はマリアに似過ぎている。
目の前の女性とどう接すればいいか、俺はだんだん分からなくなってきていた。



